�@
�_�@�@�d
|
�u�u�_�d�v�͓��{��ƗÖ@�m����j���[�X�ɒ���f�ڂ����O�������Ŏ��M����G�b�Z�[�ł��B�܁X�̋L�̂悤�Ȏv���ŁA���̂Ƃ��ɕ����v���������Ă��܂��B��������E�ɏA����2003�N���猻�݂܂ł̂��̂����ׂČf�ڂ��܂����B���̐܁X�̎������f���o����Ă���悤�Ɏv���܂��B
|
ZIZI-YAMA  |
��������
�@�u����������ȁv�u���ʂ�����ȁv�ƌ����Ĉ�����B�n�C�ƕԎ������Ȃ���A�v���A�����Ԃ��͂��Ă����B���Ă����Ƃ�����薳���͂��Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ������A��ނȂ������B����������Ȃ��A������[�������邽�߂�������Ȃ����A����͂���Ƃ��āA���Ȃ���Ȃ�Ȃ����������ɔ�ׂāA���ʂ́A���悤�Ǝv���Ă������Ƃ͂قƂ�ǂȂ��B���ۂɂ́A�������������ʂ�U��Ԃ��Ă݂��Ƃ��ɁA�������ʂȂ��Ƃ����Ă��܂����Ǝv������̂����\����悤�Ɏv���B
�@�����Ƃ��A�u����������ȁv�u���ʂ�����ȁv�Ƃ悭����ꂽ�N��̎��ɂ́A���������ʼn������ʂ��́A�悭�킩���Ă��Ȃ������Ƃ����̂������ȂƂ��낾�B�����Ȃ��Ƃ��ɍŏ����疳�������ʂ��Ȃ��ɂ͂ł��Ȃ��B�o���̂Ȃ����Ƃ�����Ƃ��ɂ́A�������������Ă݂邵���Ȃ��B�������āA��������͖������ƋC�����A���̖����Ő��܂ꂽ���ʂɋC�����B��Ȃ̂́A���̏����̖����Ɩ��ʂ��B���Ȃ����Ƃ��Ǝv���B�B�����A���Ă��܂��������Ƃ����Ō��������ʂ����ɐ������A���̂�Ƃ肪����ƁA�������d�˂Ă��Ă킩�����B
�@���ʂƂ݂�����̂���Ƃ肾�Ǝv����悤�ɂȂ�A��Ƃ�̂��߂ɖ��ʂ��c�����ƂŁA���������Ȃ��Ă��ނ悤�ɂȂ�B���������āA���܂ꂽ���ʁB���̖����Ɩ��ʂ��B�����Ƃ��鎞�ɁA����Ȃ閳�����J��Ԃ�����ɂȂ�A�\�������Ȃ������V���Ȗ��ʂ����܂��B
�@�����v���ĐU��Ԃ��Ă݂�A���N1�N�́A�킪�����d�˂��ϔN�̖����ƉB���Ă������ʂ����E�ɂ����N�������悤�Ɏv���B���̏d�˂Ă��������ƉB���Ă������ʂ��A�V�ЂƐl�Ђɂ��T���C�ɘR��o�������o�����N�������悤�Ɏv���B�������A����ł��܂��B������Ȃ����ʂ��B�����Ƃ��閳�����d�˂Ă���B���ꂵ�������������B���ꂪ���ނ���Ȃ閳�ʂ�N��������̂��낤�B
�@�K�v�Ȗ��ʁi��Ƃ�j�����̐���Ɏc�����߂ɁA�킽�������͍��A���������i�w�́j�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���c���c���K�v�͂Ȃ����A���ꂫ�������R��Ԃ��Ȃ��؋��̂悤�Ɏc���̂͂悭�Ȃ����낤�B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���{��ƗÖ@�m����j���[�X 358�A2011/11 |
|
1����1��
�@�߂܂��邵���A���낢��Ȃ��Ƃ��N���A�\���ȑΏ����ł��Ȃ��܂�����i���ځj���悤�ɉ߂��Ă䂭�B�Q�Ăӂ��߂��A���Ԃɒǂ��܂����ĉ߂��Ă��A1����1���B�������Ǝv�l�̐��ʁi�݂Ȃ��j�����䂽���Ȃ���߂����Ă��A1����1���B�ЂƂ̐����I�@�\��\���A�����Ă������Ղɏ����ł��邱�Ƃɂ́A�l��������Ƃ͂����Ă��A�q�g�Ƃ�����̑��̂Ƃ��Ă݂�Ό���ꂽ�͈͂ɂ���B
�@�ЂƂ͂��̐����̂��߂Ɂu����Ɉˑ�����B��̚M���ށv�Ƃ������̂�Bartholomew�B�ЂƂ̐����̑唼�́A������g�����܂��܂ȍ�Ƃ��Ɗ����ɂ��\������A���̍�Ƃ��Ɗ�����ʂ��āA�q�g�͐l�ɂȂ�A���̐i�����x�����Ă����B�n�T�~��V���x���ȂǁA�g�̂̋@�\��₤�����u�Ă��̌����v�𗘗p���A�͊w�I�G�l���M�[�͈̔͂Ő��g�̐g�̂����݂����͂��Ïk�E���傳���邱�ƂŁA�ЂƂ͎��R�ƑΛ����������Ă����B
�@�����āA�͊w�I�G�l���M�[���z����G�l���M�[�Ƃ��āA���z�̌b�݂��A���Ǝ��Ԃɂ��n���E�Ïk������ꂽ���ΔR����A�n���̏d�͂Ɛ��̏z�A���̗́A���z���A�g�Ȃǂ�d�C�G�l���M�[�Ƃ��ė��p���邱�ƂŁA�傫�Ȑi���𐋂����B�������A���̗��ւ��ƌ����Ƃ������̖���m�����l�Ԃ��A����̎�ŏ����ȑ��z�i�j����ɂ��G�l���M�[�j����낤�Ƃ���������A����͑傫���ς�����B�L�x�ȃG�l���M�[�ɂ��A1���Ƃ������Ԃ́A���ւ����z���āA�߂܂��邵���l��ǂ����Ă鑶�݂ɕϖe���Ă��܂����B�n�\���`�[�^�[������������V�����A����c�o����葬����Ԕ�s�@�A�C���~���傫�Ȑg�̂ł킽���ʂ̌������^�ԃ^���J�[�B����͗��ւ��ƌ����������炵�����A1���Ƃ������̂�Ƃ��D���Ă��܂����B�n�k�ƒÔg�������R�ЊQ�A���z�[�����������˂����ƂŋN�����l�Ёi�������́j�A���������́A������x�A��ƓI���݁A�l�Ƃ��Ă̐����I�@�\��\���őΏ��ł���1���̎��̗�������߂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��悤�Ɏv���B�����Đ��A����������K�����x�A��ʗA������n�Y�n���A���낢��Ȍ��������K�v���낤�B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���{��ƗÖ@�m����j���[�X 354�A2011/7 |
|
�@�n�E�p�E�[
�@�ЂƂ̏o��A�w�ƁA����A�����A�d���A�����Đl���A�����R�̐A�����璎�����܂ŐX�����ۂ��ׂĂɎn�܂肪����A�����p���i�p���j������A�[�߂ǂ��i�I���j������B3���A4���̔N�x�ւ��́A�����������낢��ȋ��̒��ŁA�������̐�������Ɏd���Ɋւ����肪�d�Ȃ鎞���ł���B
�@���N�����ꂼ��ɁA�����������܂��܂ȁu�n�v�u�p�v�u�[�v���I���āA�V�����N�x���}����ꂽ���̂Ǝv���B�₩�ȓ]�������҂�����(�܂育��)�̐��E�́A�u�n�v�͑����Ƃ����҂�����������̂ł��������A�u�p�v�Ńh�^�o�^�A�W�^�o�^���������B�Ȃ����ƌ��ɂ��邱�Ƃ��ׂĂ��A�ꓖ����I�Ƃ������A���Ƃ��݂��Ƃ��Ȃ��A����Ă��܂��悤�ȁA�u�[�v�Ƃ������u���v�̗l����悵�Ă���B���ǂ��̏����ȋƊE���A���̍����Ɋ������܂ꂽ�������łƂ������A��(�܂育��)�̎d�g�݂₻�̗��\���ꕔ�_�Ԍ���@��������B���������Ƃ��ɂ́A�{���ɂЂƂ̕i�ʂ��I��ɂȂ�Ƃ������Ƃ��A���߂Ď��������B
�@���������s�m���Ȏ��̗���̒��ɂ����āA�킪��ƗÖ@�Ƃ��������ȐE�킪���̍��ɒa������45�N���o�B�V���ȁu�n�v�Ɍ������Ăǂ̂悤�Ɉ����p�����A�]�����邩�A�u�p�v�̂���悤������Ă���B���́A�������g�́u�[�v���l����N��ɂȂ�A���A�ڑO�ɂ���u�n�v�ւ̊֗^�̎d�����ǂ����邩�A���ꂵ���Ȃ��悤�ɁA�ł���Εi�悭�Ǝv���}���Ă���Ƃ��낾�B�F����͂ǂ��Ȃ̂��낤�B���߂Ắu�n�v���}����V�l�A�u�p�v���l���āu�n�v�Ɍ����������A���Ɠ������u�[�v���͂�Ȃ�Ɣ[�߂邽�߂Ɂu�n�v��}��l�A���ꂼ��̗͂��g�������āA2011�N�x�̍�ƗÖ@�́u�n�v�̈���ݏo�������B
�@2011�N�x�̂킪���̍�ƗÖ@�u�n�v�̎�Ȃ��̂Ƃ��ẮA��16��WFOT���2014 Team Japan�̎n���J�n�A���v�@�l���̏����A��c�����ւ̈ڍs�A�V�̐�1�����I����������ƗÖ@�m��������I���Ȃǂł��낤���B�����Č��t�ɂ͂��Ȃ����A�ł��邾�������A���܂������Ɂu�[�v���I���Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ�����B���āA����ƒx�ꂸ�Q��܂��傤���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���{��ƗÖ@�m����j���[�X 351�A2011/4 |
|
�@���R�E�K�R�E���R
���R�Ƃ́A�K�R���̌��@���Ӗ����A���O�ɗ\�����邱�Ƃ��s�\�Ȃ��ƁA���邢�͂��ꂪ�N����Ȃ��\�������������Ƃ��������ꍇ�������B�u���܂��܁v�Ɠ��`�ŁA�u�v������炸�v�u�}�炸���v�Ƃ����Ӗ��ŗp������B����ɑ��A���̒��Ɍ����邠����o�����́A����ɐ旧�o�����ɂ���Č��肳��ċN����Ƃ����u����_�v�ł́A�u���R�Ƃ������Ƃ͖������ׂĂ��K�R�ł���v�Ɛ����B�K�R�A���Ȃ킿�A�u�v������炸�v�u�}�炸���v�u�`�������͖��������̂Ɂv�N�������Ƃ́A���ׂĂ�������ׂ����ċN�����Ƃ����B
�@���ʓI����_�ł��낤���m���I����_�ł��낤���A�����_�ł����Ă����܂�Ȃ����A�ǂ����������̓���́A�v���������Ă����̒ʂ�ɂ͍s�����A���̂悤�Ȃ��Ƃ��N����Ƃ͎v�������Ȃ��������Ƃ��A�������d�Ȃ��Ă��낢��Ȃ��Ƃ��i��ł����B�������āA���Ƃ��i��ł������ŁA�{���ɂ������Ǝv���]�n�������A�����������邵���Ȃ��Ȃ�Ǝv���悤�Ȃ��Ƃ������悤�����A�������Ȃ��̂��낤�B
�@���ꂱ�����K�R�Ƃ��������������邪�A���������_�c�͂��Ă����A���̓��O�̂��܂��܂ȃo�����X���h�炬���ʂ������ɂ����ɂȂ��Ă���B�킪��ƗÖ@�̋ƊE���A����ׂ����ĂȂ̂��A�����邱�Ƃ��ł��Ȃ������̉ۑ������ĐV�N���}�����B5�5�헪����A��16��WFOT���2014
Team Japan����1��̍�����c���J���n���J�n�A���v�@�l���̖��A���E��⑼�c�̂Ƃ̘A�g�̂�����ƁA�d�Ȃ�ۑ�̒��ŐV�̐����D�o����q�C�i1���ځj���I���A���߂Ă��̐����������I���̔N�B�܂��܂��u��ƗÖ@�̒m����Z�p���K�v�Ƃ���邪�A��ƗÖ@�m�͓��������v����B���Ƃ������ɂƂ��āu�v������炸�A�}�炸���v�����ꂽ�ł������Ƃ��Ă��A��ƗÖ@�̃T�[�r�X��K�v�Ƃ���l�����ɑ��āA�����ǂ̂悤�ɒ��邩�A��������ƗÖ@�m��l�ЂƂ�̎��o�Ɗm���ȍs���������N�ł���B���ׂĂ����R�A�K�R�����A���R�Ȑ���s���Ƃ��Ď~�߂Ԃ�Ȃ��N�ɂ��悤�Ɛ����ĐV�N���}�����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���{��ƗÖ@�m����j���[�X 346�A2011/1 |
|
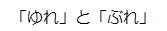 �@ �@
�@���������ɕs�v�c�Ȍ��������p�������n�߂��B�������O�p�ŁA��ɂȂ�ɂ�~�`�ɂȂ铌���X�J�C�c���[�B634���A�������d�g���Ƃ��Đ��E��̍����ɂȂ�Ƃ����B634���̍����́A���̈�т��������ŕ����i�ނ����j�̍��ƌĂ�Ă������Ƃɂ��Ȃ��634�i�ނ����j�ƌ��߂�ꂽ�ƕ����B�d���̐S�����U�Ȃnj×��̑ϐk�Z�p�ɓ��{�̍ŐV�Z�p����g�������ʕt���@�\�����p�����\���ł���B�S�����̃^���[�{�̂ƓS�R���N���[�g�\���̐S���i�������j�̓�d�\���ɂȂ��Ă��āA�S�����U��q�̋@�\���ʂ����{�̂Ƃ̗h��E���邱�ƂŁA�ɂ₩�ɗh��Ȃ���h����z������B���������Ă��h��Ȃ��\���́A�ꌩ���Ɍ����邪�A����^���J�[����u�̂����ɐ^����ɂȂ��Ē��Ɛ��j��̂悤�ɁA�Ƃ����₷���B
�@�\�����傫���Ȃ�Ȃ�قǁA�h��Ȃ���A���̗h����z�����đ�h���h���A���������_��ȍ\�����K�v�ɂȂ�B�g�D�������ł���B���A���E�����h��̎���ɓ����Ă���B�킪���̍s�����A�ǂ��ŁA�ǂ̂悤�Ɏ��܂�i���܂�H�C�܂�H�j�̂����ʂ������Ȃ��h�ꂪ�����Ă���B�킪��ƗÖ@�ƊE�����̂�����������̂悤�ɗh��Ă���B�������g�D���A�h��Ă���Ƃ��ɂ������̖{���������B�h��Č`���������̂ƁA�h��Đc���͂�����ƌ����Ă�����̂Ƃ�����B�u���v���P����Ԃ��甲�������A�]����}��`�����X�ł����邪�A�u���v�Ɍ˘f�������������ƁA�傫���u�Ԃ�v�Ă��܂��B��ƗÖ@���������Ă���u���v���`�����X�Ƃ��Ċ��������B�h��܂��Ɠ��肷�����ɁA�u���v�Őc������߂悤�B�����āA�u��Ƃ�p���Đ����@�\���A�Z�X�����g���A�����@�\�Ɏx�Ⴊ�����Ă��A�����ɕK�v�ȓ��X�̊������s����悤�A��Ƃ��������ĉ�������v�A���́u�ЂƂƍ�Ƃ̊ւ��v��p���u�ЂƂ����������߂��v����������Ƃ�����ƗÖ@�̌��_�ɗ����߂肽�����̂ł���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���{��ƗÖ@�m����j���[�X 344�A2010/9 |
|
�@�n���̗����ɍs���Ă����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@ ��15���WFOTCongress�`�����ɎQ�������B���p���܂߂ĕГ����悻30���Ԃ̋����͋߂��ĉ��������������B�o�x��ܓx���炷��A���{�ƃ`���͂��傤�ǒn���̗����i�Ɂj�ɂ�����B���L�V�R�ɍs�����Ƃ��������ł��������A�`���̐l�����ɂ����Ƃ������Ȃ��e�ߊ����������B��T�ɂ͌����Ȃ����A���ϓI�ȓ��{�̍������Ƃ͂�͂�قȂ�悤�ɂ݂���A���̋C�����ŁA�����炩�ŁA�̂ŁA���邢���e���n�̐l�����Ɋ�����e�ߊ��͉��ɂ����̂��낤�B���y�������ŁA���{�̉��y�Ƃ̓m�����炵�ĈقȂ�̂ɁA���ɐe�ߊ�����������̂�����B
�@���������̂�5�����{�A���{�͏��Ă̋G�߂ŁA�ɂ̃T���e�B�A�S�͏��H�B���łɉ����A���f�X�̎R�X�̒��͔����ቻ�ς��A�X�H���͍g�t���n�܂��Ă����B���O�������Ă���ƁA������ăA���[���`���̋�V���l�A�^�E���p�E���p���L�̃M�^�[�ɂ��e�����w�C���f�B�I�̓��x��������ł����B���̈����������e�ߊ��͂Ȃ낤�A���ɂ��̓y�n�̕��y�ɍ��킹�Ē�Z����_�k����̂Ƃ������R�Ƃ̊W�̎������ɊW������̂�������Ȃ��Ə���ȑz�������Ă݂��B���R���̂��̂�����A�n�Y�n���Ƃ�����A���̓y�n�̌��ƕ��̓��������݂����������琶�܂�鈣�D�Ȃ̂�������Ȃ��B����A����ȏ�Ɋ����邠�̉��������A�e�ߊ��́A�k�C���h�̃��V�P�[�V���ł������̂͂���ł����������̂Ɠ�������������B
�@����́A�Ȋw�ƍH�ƋZ�p�̐i���ɂ�萶�ݏo���ꂽ�A���Ə���ӂꂽ���E�A��������������Ȃ��Ă��H�v���Ȃ��Ă��悢�A�R���r�j�����̂悤�ȗ��ւ��̒��Ŏ����������������̂ւ̋��D�Ȃ̂�������Ȃ��B�ЂƂ̕�炵�̉c�݂Ƃ��̏�Q�Ɋւ�邱�Ƃ�(�Ȃ�킢)�Ƃ���҂Ƃ��āA�����Ă��鐶�����̑r���ւ̐S�̒ɂ݂ɂ����̂�������Ȃ��B����̒n���̗����ւ̗��œ������n���A�ٕ����Ƃ̏o��ŋC�Â��A�����������������́A���������Ă�����̂ւ̎v���ł������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���{��ƗÖ@�m����j���[�X 341�A2010/6 |
|
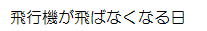 �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@��15���WFOT���E��5���Ƀ`���ŊJ�Â����B�`���͓�����170�q���܂肾���A�ԓ��߂������ɂ̋߂��܂�4000�q�����k�ɍג��������B���{�̍��y�̖�2�{�̓y�n�ɁA���{�̐l����10����1���܂�̐l�X����炵�Ă���B���E���́A���̃`���̎�s�T���e�B�A�S�ŊJ�Â����B�T���e�B�A�S�Ɠ��{�́A����13���ԁA�����ɂ��Ė�17000�q�̈ʒu�W�ɂ���B���ꂼ��n���̔��Α��ɂ���悤�Ȃ��̂ŁA�̂̑D���Ȃ�1�����߂������������A���Ȃ��s�@��30���Ԃ��܂�ŖK��邱�Ƃ��ł���B��ǂ�قǑ�����ʂɔ�ь������ƁA�l�Ԃ���������ɂ͕����̈ړ����������Ȃ��B�����Ė{���̈Ӗ��ł̗����ƘA�g�́A���݂�������Ȃ���b���������Ƃɏ�����̂͂Ȃ��B1�����Œn���̔��Α��ɂ��鍑��K��A������Ȃ���b�����Ƃ��ł���B��s�@�����邩�炱���\�ȍ�ƗÖ@�̐��E���Ƃ�����B
�@�Ƃ͂����A���̗��ւɊ��S���Ȃ���A�ЂƂ̕�炵�̉c�݂Ƃ��̏�Q�Ɋւ�邱�ƂƁi�Ȃ�킢�j�Ƃ����ƗÖ@�m�Ƃ��ẮA�������G�Ȏv��������B��s�@�ɂ��ړ������ʂɂȂ����̂�20���I�����ɂȂ����Ă���ł��邪�A�܂������Ԃɐ��E���ɕ��y���A�l�ƕ����̈ړ��̎��Ԋi���A�n��i�����ꋓ�ɏk�߂��B����������́A���ΔR���ł���Ζ����ʏ���邱�ƂŒz���ꂽ���̂��B�n���̗��j���炷��A�u�����x�̔N���ʼn��ΔR����H���Ԃ��Đ��܂ꂽ�ɉh�A���̔ɉh���킸�������I���炸�ŏI�����}���悤�Ƃ��Ă���B������̃G�l���M�[�Ɋւ��ẮA���܂��܂Ȍ������Ȃ���Ă��邪�A�Ζ��ɑ�������ő�ʂȃG�l���M�[���J������Ȃ�����A��s�@����Ȃ��Ȃ���͂��������Ȃ��B��s�@����Ȃ��Ȃ���A����́A�ߗނ���p�i���͂��߂Ƃ��A�����̐Ζ������i���p�������A�l�╨���̑�ʈړ����ł��Ȃ��Ȃ�A�������ׂĂ�傫���ς��Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ�����B�`�����̎葱�������Ȃ���A��s�@����Ȃ��Ȃ���̐����ƍ��ی𗬂ɂ��Ďv�������点�Ă���B��s�@�̔�Ȃ��Ȃ���̑O�ɁA����͒n�Y�n���ɋ߂������̖K��d�d�B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���{��ƗÖ@�m����j���[�X 338�A2010/3 |
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |
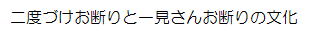 �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@
�@���͒ʓV�t�A�W�����W���������ɂ͋��J�c����������ׂĂ���B�����ł́u�\�[�X�̓�x�Â��֎~�v�͏펯���B�������̃o�b�g�ɓ������\�[�X���q�����p�Ŏg�����炾�B��x�Â�����ƎG�ۂɂ܂݂ꂽ�����������낤���W�ɂȂ邩�炾�낤���B�N�ł������u�ĂȂ������B���̑���ɁA�M���M���̐ߓx�ł��݂��̈��S�E���S��ۏႷ��B���ꂪ�u��x�Â����f��v�̕����Ƃ�����B
�@����ɑ��āA�������f�蕶���ł��A���s�ɂ͋_���̉ԊX������𒆐S�Ɂu�ꌩ���f��v�Ƃ�������������B���s�ɏZ��ł��Ă��A���̓X�ɂȂ��݂̐l�̏Љ�Ȃ��Ɠ���Ȃ��B�f���̔���Ȃ����̂����Ȃ����ƂŁA�`���╶�������B�~�V�����������ŗh�ꂽ���A���ꂪ�u�ꌩ���f��v�̕����ł���B�@
�@�N�ł�����邪�A���ꂾ���͎��Ȃ��Ƃ��f��Ƃ��������ƁA���ꂪ���Ȃ��l�͂��f��Ƃ��������A�����̂悤�Ɍ������̕������̂���ׂ荇�킹�ɂ���A�������������O�\�ΑD�Ō���Ă����B�u��x�Â����f��v�Ɓu�ꌩ���f��v�A���̐����Ɍ����镶���́A��������u�V�����̍D���v�ŕ�������Ď��Ƃ������Ƃł͓����ł���B�������s���A�̂��琢�E�̍��X�Ɛ[�����т��������A�����̕�������荞�݁A���ꂼ��ɓƎ��̎���������肠���Ă������ł���B�����A��̕������ɂ͐��E�e�����瑽���̐l�������W�܂�B
�@��ƗÖ@���A���ۉ��Ƃ����������Ƃ̋��������߂��Ă���B�����́A��ꉻ�Ƃ͈قȂ�B���������Ŏ炷��̂ł��A��������������邱�Ƃł��Ȃ��B�������⎩�����A���ꂼ��̑��l�ȕ����Ɖ��l�ς��ӂꂠ�����ŁA��l�ЂƂ�́u���Ȃ鍑�ۉ��v�A���Ȃ킿�������Ǝ����������ɑ��d���邱�ƂŐ��肽�B���āA�u��x�Â����f��v�u�ꌩ���f��v�A�ǂ̂悤�Ȍ`�ł���A�������Ƌ��������̍��̍�ƗÖ@�̕������݂�Ȃň�Ă����Ǝv���A2014WFOT���E���̏������n�߂Ă���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���{��ƗÖ@�m����j���[�X 335�A2009/12 |
|
�@ 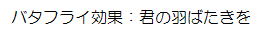 �@�@�@ �@�@�@
�u�k���Œ����H�����ƁA�j���[���[�N�Ńg���l�[�h���N����v�A�n��̖���\���ɂ͂������̃o���G�[�V���������邪�A�o�^�t���C���ʂƂ����B�ʏ�Ȃ疳������悤�ȏ����ȈႢ���A���Ԃ̌o�߂Ŗ����ł��Ȃ��傫�ȈႢ�ɂȂ�Ƃ����A�J�I�X�͊w�ɂ����錻�ۂ��g�������̂炵���B1972�N�ɁA�C�ۊw�҂̃G�h���[�h�E���[�����c�������Ȃ����u���w�\���\���|�u���W���ł̒��̉H�����̓e�L�T�X�Ńg���l�[�h�������N�������x�ɗR������ƌ����Ă��邪�肩�ł͂Ȃ��B
�@�R�����`�͂��Ă����A�����Ӗ��ō�ƗÖ@�̐��E�Ƀo�^�t���C���ʂ����������������Ƌ����v���B�Ȃ��Ȃ�A���A��ƗÖ@�͖L���ȉ\�����߂��傫�Ȋ�@�I�]�@���}���Ă��邩�炾�B������Տ����A�]���̂�������s���Â܂�͂��߂ċv�����B����A�����A�Տ��A��ƗÖ@�̂�����\���istructure�j���������A�ߒ��iProcess�j�Ɛ��ʁiOutcome�j��N�ɂ��킩��悤�Ɏ����A�{���ɕK�v�Ƃ�����ƗÖ@�̊m����}��Ȃ���A���c�����ǂ��납���������̂ł͂Ȃ����Ɗ뜜����B
�@��ƗÖ@�̎��ƎЉ�I�ȔF�m�x�����߂�ɂ́A��l�ЂƂ�̎蔲���̂Ȃ��Տ��̐ςݏd�˂ƁA�ςݏd�˂�������\������ȊO�ɕ��@�͂Ȃ��B�u�ǂ������߁v�u������l���������Ă��v�Ƃ������v�����̂ĂāA�����ɂł��邱�ƁA�������ł��邱�Ƃ����悤�B��l�̉H�������Ȃ���A���ׂĂ͎n�܂�Ȃ��B��l�̉H�������Ȃ���A�����ς��Ȃ��B
�@�u�ǂ����ō�ƗÖ@�m�������������ƁA��ƗÖ@�̐��E���ς��v�u��l�̍�ƗÖ@�m���O�ɏo��ƁA��ƗÖ@�ɑ���Љ�I�F�m���ς��v�B�ǂ̂悤�Ȍ��ۂ��N���邩�\���͂ł��Ȃ��Ă��A���߂��Ȃ���Ή����ς��Ȃ��B�k���̒��̉H�������A�j���[���[�N�Ƀg���l�[�h���N�����\���ɔ�ׂ�A�e�����������������ƁA���ꂼ�ꂪ������O�Ɍ����邱�Ƃ́A��ƗÖ@�̐��E��傫���ς��邾�낤�B
�@�u��ƗÖ@5���N�헪�v����ƗÖ@�̐��E��ς���傫�ȕ������A2014 WFOT 16th Congress�͓��{�̍�ƗÖ@���������傫�ȃ`�����X�B���A���̂Ƃ��ɌN�̉H�������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���{��ƗÖ@�m����j���[�X 332�A2009/9 |
|
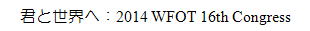 �@�@ �@�@
|
�@2008�N9��11���A�X���x�j�A�ŊJ���ꂽWFOT�i���E��ƗÖ@�m�A���j��\�҉�c�ŁA�u2014 WFOT 16th
Congress�v�̓��{�J�Â��A�_�[�o���i��A�t���J�j��A���X�e���_���i�I�����_�j��ނ��āA���|�I�����Ō��܂����B������AWFOT Congress���v�ψ���ޗLjψ����ƈψ�����o�[�𒆐S�ɁA���{���{�ό��ǂ≡�l�s�A���l�ό��R���x���V�����E�r���[���[�A�p�V�t�B�R���l�Ȃǂ̋��͂ɂ����̂ł���B���N����̏��v���������������̂ŁA���{�͂��Ƃ��A�W�A�ł����߂Ă̊J�ÂŁA���{��A�W�A�����̃��n�r���e�[�V�����̘A�g�Ɣ��W�ɑ傫����^������̂Ǝv����B�܂���N2���ɂ́A���؍���Ǝ��Îm����i�؍��ł�occupational therapy����Ǝ��ÂƂ����j�̖K�₪����A11���ɂ͊؍���ƗÖ@�w��̐ȂŊw�p�𗬂������ɒ��ꂽ�B���̂悤�ȓ��{�̍�ƗÖ@�ɑ���S�Ɗ��҂����܂�Ȃ��A���N�̕����w���2014�N�܂ŁA�w��ɖ��N�A���ۃV���|�W�E�����J�Â��A���E�̍�ƗÖ@�����m��A���{�̍�ƗÖ@�𐢊E�ɒm���Ă��炤�Ƃ��������n�܂����B
�@���̂悤�ȓ����́AOccupational Therapy���e���̕�������̂Ȃ��ŁA�ǂ̂悤�Ȗ������ʂ����Ă���̂���m�邱�ƂŁA���������g�̂����ē��{�̍�ƗÖ@�̂��������������D�̋@��ł���B�O���[�o���[�[�V�����́A�O���̂��̂𐒂ߌX�|���A�q�O��`�I�ɗ��_��f�����Љ�A��������悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B���ꂱ�������̏Z�l�̖��ӎ��ȗӎ��������炵���A���ۉ��̖����肽�r�O��`�ƕ\����̂̎��s�I�ȍs�ׂ̈�`�Ԃɂ����Ȃ��B����̊F����̍��ۉ��̑����J�����߁A������ǂɉp���؍��ꂪ���\�Ȏ�������z�u������A���ە��̍ĕҋ����A���C��z�[���y�[�W�̍H�v���i�߂Ă���B���t�̕ǂ͑傫���Ǝv���邪�A���ۉ��ɋ��߂���̂́A�_���I�Ȏv�l�͂ƓK�Ɏ����̍l����\�����鍑��́A�����̕����ɑ��鐳���������ł���B���̃x�[�X�������āA�`�ɂ�����炸�A�ϋɓI�ɃR�~���j�P�[�V������}��A�݂��ɒm�荇�����Ƃ���n�܂�B
�@2014 WFOT 16th Congress�AYokohama in Japan�́A�����̍�ƗÖ@��������傫�ȃ`�����X�B��ƗÖ@�m����ł́A�`���̃T���`�A�S�ŊJ�Â����2010 WFOT 15th Congress�Ɍ����ăc�A�[����悵�Ă���B�o�����n���̔��Α��Ɉʒu���鍑���m�A���\����A���Ȃ��ɂ�����炸�A�n���̔��Α����U������̂��y�����B�t�H���N���[���̋�V���l�Ƃ�����ꂽ���p���L�̃M�^�[�Ɖ̐����ǂ����Ă���قNj��D��U���̂��낤�B�u�C���f�B�I�̓��v���`���ňꏏ�ɕ������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���{��ƗÖ@�m����j���[�X 329�A2009/6
|
|
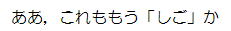
|
�@��ƗÖ@�̋����S����20�N�ɂȂ�B�Տ��œ����Ă����ƗÖ@���Ԃ⊳�҂����ɂ����镉�S�����Ȃ��������Ƃ������ƂƁA�Տ��o�����Ȃ��w�������ɂ��Ƃɂ��u�`�ł͓`���ɂ������Ƃ������ł������ł���悤�ɂƁA�]�����K�͎�������ƗÖ@�m�Ƃ��Ă̗Տ����̈ێ��ƗՏ������̃t�B�[���h�̈�Ƃ��Ċ֗^���Ă����w�a�@�̐��_�ȂŎ��݂Ă����B�Տ��o�����Ȃ��w�������ɑ���u�����A�������B���ꂪ�����Ȃ̂��v�Ƃ����u�C�Â��̊w�сv�̎��݂ł���B����ł��A�]�����K�ł́u�����������ƂȂ̂��ȁv���x�ŁA�Տ����K�ŏ��߂Ēm�����悤�Ȃ��Ƃ������A�Տ����n�߂�4�A5�N���Ă���u�����A�����������v�Ƃ������ƂɋC�Â��B�����������̂��Ǝv����20�N�A�ŏ��̔����J�����Ƃ��ɂ����҂̐ӔC�Ƃ��āA�������֗^���Ă���Տ��̏�ɂ����鋤�L�̌���w������������܂ł̐����̒��Ōo�����Ă���ގ��̌��A�����āu���Ƃ������̂悤�ȁv�Ƃ�����g�\���Ȃǂ���g���āA�`����H�v�����Ă����B�������A�N�X���̍H�v�������Ȃ��Ȃ�A����Ȃ��Ƃ܂łƎv���悤�Ȃ��Ƃ��A���ꂱ���u���葫���v���ċ����Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ��ӂ��Ă����B���낢��ȕ\���œ`���Ă��u�H�v�Ƃ����\��������҂����Ɂu�����A�N�����ɂƂ��Ă͂���������������v�Ǝv�킸���ɂ����Ƃ��A����ɏd�Ȃ����u�H�v�u�H�v�̕\��B�u�����v���u�����v�Ȃ̂��ƁA���炽�߂āu�����v���Ēm���Ă���ƕ����Ă݂���A�u�l���v���ƌ����A�u�l���v���ĉ����Ɣ��ɕ����Ԃ����܂B�ǂ����u�����v���l���n��Ǝv�����炵���B�b�̗���̒��́u�����A����������������v�ɓ��Ă͂߂āA�����Ƃ��Đ��肽���ǂ������l���邱�ƂȂ��A�u����v��u�����v��������ꂽ�B�u�����v���u�����v�ɂȂ��Ă���̂ɋC�Â����ꂽ�u�Ԃł����B
�@�N�n�߂ɁA�F���ƗÖ@�m�̍X�V���C�ł��b������@��������B���ꂱ��1���b�������10�ȏ�킩��o����ς܂ꂽ��ƗÖ@�̐�B�̊F����ł���B�u����v�͂Ƃ������u���葫���v���u�g�̂Ŋo����v�Ƃ������Ƃ��u����v�ɂȂ鐢�オ��ƗÖ@���w��ł��鎞��B�ǂ����u�g�̂Ŋo����v�o�����o����ƗÖ@�̐�B�Ƃ��āA�F���ƗÖ@�m�̍X�V�����܂��Ă��������A���̌o�����`�Ƃ��Ďc���A�u���葫���v�A��ƗÖ@��ʂ��玿�ɕς���͂ɂȂ��Ă������������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���{��ƗÖ@�m����j���[�X 326�A2009/3
|
|
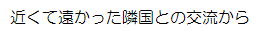
�@���ɍg�t�������̊؍��ɁA��؍�Ǝ��Ît����Ƃ̊w�p�𗬂̒���ʼn�A���ە��S�������Əo�������B��16���؍�Ǝ��Êw��ŗ����̉�ɂ�钲�s���A�˗��̂������u���{�̐��_�ی����x�ƍ�ƗÖ@�v�Ɋւ���u�����I�����B���������Ċ؍��̐��_�ی�����ƍ�ƗÖ@�̉ۑ�Ɋւ���V���|�W�E���ɂ��A�}篓��ʎQ�������܂�R�����e�[�^�[�Ƃ��ĉ�������B
�@�؍��̍�ƗÖ@�̗��j���Ђ��Ƃ��ƁA���N�푈�̎��ɕč�����William Rush Dunton�������čs�����̂��ŏ��ŁA���̌���{�Ƃقړ��������ɓ��������݂��Ă���B�؍��̍�ƗÖ@�m��1�����a�������̂�1969�N�ł��邪�A���K�̍�ƗÖ@�m���炪�n�܂����̂�1979�N�̉�����{�Z�����߂ĂƂ������B�w��Ƃ��Ă̊�����1983�N�ɊJ�n���A1993�N�ɑ�؍�Ǝ��Ît������F����A���N�ɉ�����{�Z�ő�w�@���炪�n�܂�A1997�N�Ɋw�p���n���A1998�N��WFOT�����Ƃ������j�����ǂ��Ă���B���ݗL���i�Җ�3500���A4�N����w17�Z�A3�N���Z����w26�Z�ɍ�ƗÖ@�w�Ȃ�����A�����w����͖�1500�l�ƁA�K�͈͂قȂ邪�킪���̍�ƗÖ@�̗��j�̏k�}���}���ɂ��ǂ��Ă���Ƃ�������������B���_�ȍ�ƗÖ@�Ɋւ��ẮA�܂��f�Õ�V�̑ΏۂƂȂ��Ă��炸�A��ƗÖ@�ɗނ�����̂́A���_�Љ�Ǝm�Ƃ������̂ŎЉ���m�Ƃ��ď���̌P�������҂��s���Ă���A��ƗÖ@�m�̐��_�Ȉ�Âւ̎Q���ɑ��ẮA��t�̒c�̂̒�R���傫���ƕ����B����͐����ł��邪�m�F���ꂽ���̂ł͂Ȃ��B�Љ����傫���ω����钆�ŁA�e���̍�ƗÖ@�����ꂼ��̍��̏�܂��Ȃ���傫�ȓ]���������Ă���B
�@�߂��ĉ����������Ƃ̍�ƗÖ@������w�p�����𗬂́A�������ɂ��܂��܂Ȃ��Ƃ��C�Â����Ă���邾�낤�B�����Ƃ̊w�p�𗬂�JICA�̊֘A�ł��łɎn�܂��Ă��邪�A�A�W�A�����m�n��̌𗬂͎n�܂�������ł���B��������Ă݂Ă킩��B����́A�Ζ��{�݁A�̈�A�o�g�n�A�Ƒ��A���ƂȂǁA�������������������W�c���ׂĂɌ����邱�Ƃł���B���Ƃ̌𗬂��͂���WFOT���E���̏��v�́A�r�O�A�q�O�A��́u�͂������v�̎������痣��A�L������ŁA���̍��Ƃ��̍��Ő��܂ꂽ��ƗÖ@���������ǂ��@��ɂȂ邾�낤�B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���{��ƗÖ@�m����j���[�X 323�A2008/12 |
|
�@�u�n�Y�n���v�̍�ƗÖ@��
�@�R����̍����ɂ��A�ߑ�Ƃ����V�X�e���̍\���ƌ��ׂ��݂��Ă����B���ɂ��}�l�[�Q�[���̉e�������邪�A�m���ɏ���F�T���x�������A�n���Ƃ����V�X�e���ɂ�����l�Ԍ��̌������������p�������n�߂��Ƃ�����B�l�Ԃ́A���ɋߑ�ɂ����ẮA���ƕ����ʂɑ����ǂ��ւł��Ƃ����ړ��E����V�X�e���ɂ��A�傫�Ȕ��W�𐋂��Ă����B�l�ނ̂���悤���炷��A���̕�������ς��邱�Ƃ͓���ł��낤���A���ʂ̕��@�ƕ��ɂ��ẮA���Ȃ�������Ȃ�������}���Ă���B�n���Ƃ�����̃V�X�e���̒��ŁA���Ύ��Y��H���Ԃ��`�Ŕ��W�𑱂��Ă����l�Ԍ��Ƃ�������Ȑ��Ԍn�ɉA�肪�݂��Ă����Ƃ����Ă��悢���낤�B����ۑ������������ƂŁA�n�捷�⎞�ԍ��A���i���A���R���̉e���Ȃǂ�Ƃ�Ă������A���̂��߂ɑ�ʂɏ���Ă����G�l���M�[���̌͊��ƕۑ���ړ��ɂ�镨�̎��̕ۏ�̒ቺ�Ƃ��������肪����B�u�������֗����v���u�������Ȃ����Ƃ̎��v�̌������Ƃ������悤�B
�@�J�ͥ���ԥ�G�l���M�[������āu�������v���Ƃ���������ւ������邪�A�u�������v���Ƃŗ������Ȃ��Ȃ���̂�����B����x�u�������Ȃ��v���Ƃ̑�����l���Č��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����͔_�Y���́u�n�Y�n���v�͂������̂��Ƃł��邪�A��Â���x���Ȃǂɂ��Ă�������̂ł͂Ȃ����낤���B�����Ɋւ�鎡�ẤA�ړ�����ނȂ����A�\�h��{���̐����Ȃǂ́u�n�Y�n���v���ǂ̂悤�Ɋ�������������Ă���悤�Ɏv���B��ƗÖ@�m�����2008�N�`2012�N��5���N�ɁA��×̈�ƕی������̈�̍�ƗÖ@�m�z�u���5:5�ʂɂȂ�悤�ɂƂ������Ƃ�ڎw���A�n�搶���ڍs�x���̐��i���u��ƗÖ@5���N�헪�v�Ƃ��Čf�����B�u���@��Ò��S����n�搶�����S�ցv�Ƃ������A10�N�v��Œ���ď㔼���̏I�����}���Ă��鍡�A�u�n�Y�n���v�̍�ƗÖ@�������g�����f�B�B�������A�n���̐H�i�E���R�̏{�̎����̐H�i�̂��N�ɗǂ��Ƃ����u�g�y�s��v�̂悤�Ȕr�O�I�ȍ�ƗÖ@���w���Ă̂��Ƃł͂Ȃ��B�K�v�Ȓm����Z�p�͂ǂ�����ł��ړ������A���̒n��̕�������y�����������A�n�搶�����S�̍�ƗÖ@�ł���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���{��ƗÖ@�m����j���[�X 320�A2008/8 |
|
�@�����ƌ����������Ă�
�@�u���Ƃv�Ƃ͕s�v�c�Ȃ��̂��B�������ꌾ�ŃX�b���D�ɗ����A�[���ł�����̂�����A�����������A�{���݂̂��Ȃ����̂�����B���ׂĂ������ł͂Ȃ����A�����̘A�Ȃ�⑽����������Ȃǂɏo��ƁA�{���̈Ӗ����݂����Ȃ�ƂȂ��������������Ă��܂��B
�@4���ɁA�c�ɂň�l��炵�����Ă���ꂪ�A�������҈�Ð��x�̑ΏۂȂ̂łƁA�ی��̉��u�n�ؖ��ԋp�̒ʒm���������B�u��Q�Ҏ����x���@�v�u�������҈�Ð��x�v�ƁA�����T�[�r�X�A����S��ÁA����҈�Ô�Ȃǂ̖@���x�̉������������ł���B��������A�����Ă͒ʂ�Ȃ����̂���ł��邪�A�܂�Ƃ���͍s�\���Ȍ��ʂ̍������S�̍s���Â܂肪�����炵�����̂��B
�@���炷��A�����ȕ��S���A���ꂼ�ꂪ����Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ́A���ꂪ�l���Ă���ނȂ����ƂƎv����B�������A���܂�ɂ������Ƃ͎v���Ȃ��B���S�̊z�̖��ł͂Ȃ��A�����S�̂Ɋւ�镉�S�x�������Ƃ͎v���Ȃ��̂��B�����̗͂̎ア�҂ɕ��S���d���̂��������Ă���悤�Ɏv����B�����x���Ƃ����Ȃ���A�����n�[�h���ŁA�����̑������������Ă���B�ǂ��l���Ă��A��ς����NJ撣���Ă݂悤�Ƃ͌����ɂ������A���������C�����ɂ͂Ȃ�ɂ����B�������҈�Ð��x�Ɏ����ẮA�u�������x�����Áv�̎����Ƃ������A�܂�ō����I�̉W�̂ĎR�ɂ��݂���B���̐��̑傫���ɁA����Ăāu������Ð��x�i�������҈�Ð��x�j�v�ƌĂъ�������A�������i�@�j����������Ȃ������肷��ƁA���悢��s�M�����̂��Ă��܂��B�ŏ�����[���̂���������₷�������͂ł��Ȃ������̂��낤���B���X�����̂ł��Ȃ����̂Ȃ̂��낤���B
�@��Q�������������̕����A��������ƗÖ@�m�Ɗւ��̐[���l�����ł���B���̐l�������u����Ă��鐶���̕s���ɁA�ǂ̂悤�ɉ����邱�Ƃ��ł��邩�B��ƗÖ@�̈˗��⏈�������A�g�߂ő傫�ȉۑ��������B�����̗]�k�łȂ�������̂����Ǝv���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���{��ƗÖ@�m����j���[�X 317�A2008
|
|
�@�~��� �| ���ꂼ���
�@
�u�~��ֈ�ւقǂ̒g�����v�i�Ԗ�\�N�F��������j
�@���t�̐����A�z�˂��ɖ��邳�������n�߂��B�~�̎c�肪�܂Ƃ߂Ă���Ă����悤�Ȋ��C�̒��ŁA����O�S�N�Ƃ��l�S�N�Ƃ�������ÖɁA���~����ցA��ցB���N���A�~�̉Ԃ��炭���߂ɂȂ�A�w���������������ގ�ɑ���f�������Ȃ���A���Ǝ����̕������Ă���B���̌��e�������ɂȂ鍠�͓��̉Ԃ̋G�߁A�������I���A�����炭�̂�҂��Ă���̂��낤�B�����w�������������A���i�ʒm�̓d���́u�T�N���T�N�v�������B���{�̉ԂƂ����A�e�Ƌ��ɍ�������ō��ԂƂ���Ă��邪�A���a�̏��߂ɂ͔~�������������������Ƙ_�����������Ƃ����B���t�W�ɓǂ܂��Ԃ͔~�������A�̂́A�Ԍ��Ƃ����Ɣ~�̉Ԃ��ς邱�ƂƂ���Ă����B
�@�~��1�N�ڂ̎�}�ɂ��Q�����Ȃ��B��x�����̓~�ƎܔM�̉Ă��z�����}���Q�����A��x�ڂ̓~�ɉԂ��炩����B�~�̋G��Ƃ����~�́A�S�Ԃ̊@�i���������j�Ƃ�����悤�ɁA���ׂẲԂɐ悪���Ċ��C�̒��ō炫�A�t�̖K�������B�����~�������E�ѐ��^�ȐF���e��Ƃ������ŏt������̔~�̉Ԃ́A䅓�h������z���邱�Ƃɂ��Ƃ����u�E�ρv�̏ے��Ƃ������B
�@�~�͒�������̓n���A���͊؍�����̓n���A���{�͊C���u�Ă����X�̕���������A���̍��̕��y�̒��ň�ĂĂ����B��ƗÖ@�Ƃ�����̕������n�����āA�����I���܂�A����ƍ炫�n�߂���ƗÖ@�̉Ԃ́A�ǂ̂悤�ɉԊJ���̂��낤�B�u���~�����v�A���͍��A�~�͔~�A���͓��A���͗��Ƃ��ĂƂ���ꂪ�A�����~�����������A���͂Ƃ������ׂăo���ȃT�N�����̉Ԃł���B�u���n�r���e�[�V�����Ȑ����x�����v�̉ԂƂ��āA����̊��C�ɑς��A��ƗÖ@�m����l�ЂƂ肪�A���̌������č炯�����B���N�̏t�u�T�N���T�N�v�͉̂��炾�낤�A���ꂢ�ȉԂ���������炢�Ăق����B�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���{��ƗÖ@�m����j���[�X 314�A2008/3 |
|
���ۉ��ƃO���[�o���[�[�V�����ɂ���
�@�������̂͂��܂�Ƃ��邩�͏��_���邪�AOccupational Therapy�Ƃ����A�ЂƂƂ��̐������x�����鐶��(�Ȃ�킢)���A���n�r���e�[�V�����̗��O�ƋZ�p�̈�Ƃ��ĎY�����グ�A�S�N���܂肪�o�Ƃ��Ƃ��Ă���B���̊ԁA�e���̕����A�o�ώ���͌��ς��A������E�o�ςȂǁA���ƊԂ̕����I������ړI�Ƃ������ۉ���A�n���K�͂ō��Ƃ�n��Ȃǂ̋��E���z���āA���ʂ̉ۑ�Ƃ��čl������Ȃ��O���[�o���[�[�V�����Ƃ������_����A�������̍��̐����Ɩ����̂���悤���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��ۑ肪�^���̂悤�ɉ����Ă��Ă���B��ËZ�p�͂Ƃ������A�Տ��̔w�i�ƂȂ镶���E��Ìo�ςɑ���l�����A���g�݂̈Ⴂ����AOccupational Therapy�͂��ꂼ��̍��̎���̉e�����Ȃ���A���W�Ɩ͍����J�肩�����Ă����B���łɁAOccupational Therapy��������āA���ۉ��A�O���[�o���[�[�V�����̌��ƉA���������āA����̓���������߂Ȃ��ƂȂ�Ȃ��ɂ�����Ă���B
���ۉ��Ƃ����Ă��A�����q�O��`�I�ɗ��_��f�����Љ�A��������A���D����̂悤�ȍ��ۉ��̎���ł͂Ȃ��B�_���I�Ȏv�l�͂ƓK�ɍl����\�����鍑��́A�����̕����ɑ��闝���������Ă����̍��ۉ��łȂ���Ȃ�Ȃ��B������̍���n��ł���A�����ŕ�炷�l�X�Ƃ��̐����̖����A�m���Ȉ�w�I�m���ƋZ�p�ɂ�茩��߁A��l�ЂƂ�̐����̍Č��Ɍ����āA���̎����ƓK������������Occupational Therapy�̒m���E�Z�p���s�v�ɂȂ邱�Ƃ͂Ȃ��B����͐l�ނ����̐��ɑ��݂������A�K���K�v�Ȃ��̂ł���B�������A����܂ł��x���̂悤�Ɍ��������Ă������Ƃł��邪�AOccupational Therapy�̒m����Z�p�͕K�v�Ƃ���邪�A��ƗÖ@�Ƃ������Ƃ��ƗÖ@�m�͓�������鎞�オ���Ă���B1960�N��A�킪�������f���Ƃ����č���Occupational Therapy�̕ϗe�Ɛ����c��Ɍ��������܂����s�́A�����đ��R�̐ł͂Ȃ��B
�@���̂悤�ȏ̒��ŁA���{��ƗÖ@�m����͒����v��̈�Ƃ��āA2014�N��WFOT���E��c���v�̉^�����A�ψ����ݒu���J�n�����B���v���ł��Ă��ۑ�͑傫�����A���łɁu�q�O�v�u�r�O�v�̊Ԃŋ���I�Ȏ���Ř_�c���郌�x���ł͂Ȃ��BWFOT�̂���悤�A������Occupational Therapy���e���łǂ̂悤�ȋ@�\���ʂ����Ă��邩���������A���{�̎�����e���ɓ`���A�X�̍�ƗÖ@�m�������̖ڂ̑O�ɂ��鎄�����̃T�[�r�X��K�v�Ƃ��Ă���l�����ɁA�����ǂ�����������A���̂��߂ɉ����w�ׂ��������l�����D�̋@��ł���B���ۉ��A�O���[�o���[�[�V�����͎�����L����Ɠ����ɁA�������������B���s(�͂��)�⌾�t�ɘf�킳��邱�ƂȂ��A���E�����邱�ƂŁA���������Ȃ������Ƃ��K�v�A�Ǝv���V���ȔN�ɂނ��A��ςł��������̔N�̂ł����Ƃ�Y�N�A�Y�N�B���ɂƂ��āA���N�̏���̏���108�ł͂Ȃ��A216�����Ă݂����Y�N�̔N�ł��������A�݂Ȃ���ɂƂ��Ă͂������������̂ł��傤�B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���{��ƗÖ@�m����j���[�X 311�A2007/12 |
|
���ጤ���Ɠo�^�̂����߁F�����x��
�@�����Ƃ��q�ϐ��A���Ր��Ƃ��������Ƃ�����Ă��邪�A���Ԃ⋗���̂悤�ɑ��肪�\�ȁA���l�����ꂽ�ʓI�������������Ƃ̂悤�Ɏv�������������̂ł͂Ȃ��낤���B�m���ɁA�q�ϐ��╁�Ր���₤���Ƃ͏d�v�ŁA���w�I���R�Ȋw���ߑ��w�̔��W�ɂ����炵�����b�͌v��m��Ȃ��B�������A�����Y��Y���u�Տ��̒m�v�Ƃ������t��p���Ďw�E�����悤�ɁA�ߑ�Ȋw�I��@���s���Â܂�Ƌ��������ċv�����B���̑Ώ��Ƃ��āA�m�a�l�A���I�����Ȃǂ����݂���悤�ɂȂ������A��������s�a(�͂���܂�)���Â܂�悤�Ƀg�[���_�E�����Ă��邱�Ƃ��C�ɂȂ�B
�@�g�[���_�E���̌����́A���I�����͑��肪����ŁA�_���������҂̎�ςɂȂ�₷�����ƁA���R�Ȋw�I�����ɔ�ׂāA�m�a�l�⎿�I�������Z�@�Ƃ��Đg�ɂ��邱�Ƃ̓���Ȃǂ������̈�Ǝv����B�������A�����͐��w�I���R�Ȋw�Ɍ��炸�A�����̎҂����ʂɔF�߂邱�Ƃ������ł���A�Ώێ҂̌l�I�Ӗ���[�������n�r���e�[�V�����ɂ����Ă͏d�v�ȍ����ł���B
�@��w���f���ŋq�ϓI�����������ɂ́A���ᐔ���d�v�ɂȂ邱�Ƃ��������A�������f���ɂ����ẮA��w�̎��ጤ���Ƃ͈قȂ�A�ꎖ��̓O�ꌤ���������炷���Ր��̈Ӗ��͑傫���B�ꎖ���O�ꂵ�Č������A�����Ɍ���ꂽ���ۂ���肫��Ƃ��A�ꎖ��͂��̎���������ՓI�m����Z�p�����B����Ǝv���鎖��Ƃ̎��ÓI���������z�����Ƃ��A���̈ꎖ��Ƃ̊ւ��ɂ��A���Î҂Ƃ��đ��ɗ��p�ł��邳�܂��܂ȕ��ՓI�͂�����Ă����Ƃ����o���A�Տ��Ɍg����Ă����҂Ȃ炾��ł�����͂���B�@
�@��ƗÖ@�̂d�a�l�́A����ɂ�镁�Ր��̐ςݏd�˂ɂ���B�ǂ̂悤�ȑΏۂɁA����ړI�ɁA�ǂ̂悤�Ȋւ����s������A�ǂ������ω�������ꂽ���A���̕ω��͑Ώێ҂⋤�ɐ�������ҁA���P�A���s���҂ɂƂ��Ăǂ̂悤�ȈӖ��������炵�����Ƃ������A�����ʂ������ۂ���������ƌ�邱�Ƃ��ɂ������B��l�̍�ƗÖ@�m���A��N�ԂɎ��Ώۂ���ꎖ����܂Ƃߕ���B���̎��݂����ŁA�N��30000����f�[�^���~�ς���A�����̊�ՂƂȂ�B�u�w��̂����߁v����ł��邪�A�Տ������E����ɂ�����҂̈�l�Ƃ��āA�ʓI�����A���I�������킸�A�u�x��v�ɂȂ�Ȃ��Տ��u����̂����߁v������B�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���{��ƗÖ@�m����j���[�X 308�A2007/9 |
|
�N�\�|����m��Ïk���ꂽ�ߋ�
�@��ƗÖ@�̏������A�ΏۂƂȂ�l�̐S�g�̋@�\�E�\���̏�Ԃ�m��AADL��IADL�Ȃǐ����̈ێ��@�\��1���̊�����Ԃ�m��B�����������Ƃ�����Ԃ̒f�ʂ�m�邱�ƂŁA���Â�@�\�I�ȃ��n�r���e�[�V�����͉\�ɂȂ�B�������A�Ȃ����̂悤�ȏ�ԂɂȂ����̂��A���ꂩ��ǂ̂悤�ȏ�Ԃ��\�z�����̂��A����ɑ��Ăǂ̂悤�ɉ�������悢�̂��ȂǁA�ΏۂƂȂ�l�̐����i�l���j������ɓ��ꂽ�u�ԂɁA����܂łǂ̂悤�ɐ������Ă����̂��Ƃ������Ɓi������A�������A���a���A���×��Ȃǁj���d�v�ɂȂ��Ă���B���́A����܂łǂ̂悤�ɐ������Ă����̂��Ƃ����l�����A�P���̔N�\�ɏ�����Ƃ�����ƁA���Ƃ����f�ʂł����Ȃ������Ώێ҂̏�A���̌l�̕��ꐫ���������Ïk���ꂽ�ߋ������n�߁A���ꂩ���̌��ʂ��𗧂Ă���ƂȂ�B���̂悤�ɁA�ߋ�������Ƃ������Ƃ́A�u�Ȃ����̂悤�ȁv�Ƃ�������m�邽�߂ɁA�d�v�Ȗ������ʂ����B�����āA�����N�\�Ƃ������Ԏ��ɏ����\���Ă݂�Ƃ悢�B
�@�N�\�͍���m��Ïk���ꂽ�ߋ��A���n�r���e�[�V�����ɂ����đΏۂ�m��Ƃ������łȂ��A�����������u����Ă����Ԃ�m��Ƃ��ɂ��A�N�\���傫�ȓ���������B���{�ɍ�ƗÖ@�m���a�����ĕs�f��40�N���߂��A��ƗÖ@�m�̗{�����炪�傫�ȓ]�������}���Ă���B�������A�]�����̉ۑ�́A�����Q(�Ă�)�ɂ�������̂��唼�ł���B�������A�ʁi�l���j�����������A�J��Ԃ��������傫���Ȃ��Ă���B���K�{�ݐ��A�Տ��w���҂̐��Ǝ��A���O����A���㌤�C�A�����̉ۑ�̑����́A��̑O�A��̑O�A���̍��̍�ƗÖ@�����x���J��Ԃ��o�����ė����ۑ�Əd�Ȃ�B
�@���A���̍��̍�ƗÖ@�̗��j�����Ԏ��̔N�\�ŕ\���Ă݂悤�B���̋Ïk���ꂽ�ߋ����A�f�ʂł��������Ȃ��A���Ƃ�������́u�Ȃ��H�v������Ă����B�Ȃ��A�������͍����̂悤�ȏ�Ԃɂ���̂��A���̌�����ǂ̂悤�ɒ���������̂��A���̂��߂ɍ�������������̂��A���ꂩ��ǂ̂悤�ɂ�������̂��A�����Q�܂Ȃ����߂ɁA�m���ȍ�ƗÖ@�̖����Ɍ����āA���̍��̍�ƗÖ@�̔N�\���݂�ȂŌ��Ȃ��������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���{��ƗÖ@�m����j���[�X 305�A2007/6 |
|
���l�ށH�|�����S�����M�����悤�ɂނ�
�@�Ζ����Ă���{���Z��������w�Ō��4�N����w�ɂȂ�A�ŏI�̎��K�ɏo���ꏄ��̔N���}���ē�������Ă���B�Z��Ƒ�w�ɓ��w���Ă���w���̑w�̈Ⴂ�Ȃ̂��낤���ƌ����������Ƃ��������B�m���ɁA��ƗÖ@�m�ɂȂ�Ƃ����w�������������ɓ��w���Ă���w�����������̂͑w�̈Ⴂ��������Ȃ��B���̒��ɂ́A���̎�����ς�炸�e�Ɋ��߂��ĂƂɂ����i�w�Ƃ�����(������)�̎҂ƁA���炩�ɍ�ƗÖ@�m�ɂȂ邱�Ƃ�ړI�Ƃ͂������w���Ă����҂�����B��҂Ɋւ��ẮA��ƗÖ@����̕ϑJ�Ƒ��l���Ƃ������_����A�c�_�̗]�n�͑傢�ɂ��邪�A��ƗÖ@���w�э�ƗÖ@�m�ɂ͂Ȃ炸�A�}�X�R�~�A�s���A�o�ŁA�����p����p�H�w�ȂǍL���̈�Ŋ���悤�ɂȂ邱�Ƃ��A��w����̍���̌����ۑ�ł���B��������Ă���̂́A����Ƃ͂܂������Ⴄ��ނ̊w���ł���B���łɋ��������łȂ��A���K�ŗՏ�����ɂ������Ă���݂Ȃ�����A���l�Ȍo���̐������ɂ��邱�Ƃ����邪�A����̊ȒP�Ȑ����p��Ǝv���Ă��������g�p�����o�����Ȃ��w�������̂��Ƃ��B�����S���݂�ȂŐH�ׂ悤�ƁA��ނ��𗊂��A���M�����悤�Ƀ����S�̔���������A����Ń����S���������܂ܓ��������ɁA�i�C�t�Ŕ�������悤�ɂ��Ă���w���������B����Ń����S���A�E��̐e�w�łނ��Ă�����𑗂�Ȃ���ނ��Ƃ������Ƃ��ł��Ȃ��B���܂�ɂ��s�v�c�Ȃ̂ŕ����Ă݂�ƁA����܂Ń����S�̔���ނ������Ƃ��Ȃ��Ƃ����B���������w���́A���҂���Ƃ���������b���ł��Ȃ��A�����Ȃ��ƍ���҂������B1986�N�ɐV�l�ށi����邢�j�Ƃ������t���V��E���s���܂ɑI�ꂽ���Ƃ����������A�����������l���̑���Ƃ͂܂������Ⴄ�A���B�ߒ��ɂ����鐶���o���̕s���Ƃ��������悤�̂Ȃ��w�����A���Ȃ�̊����ō�ƗÖ@�̗{���Z�ɓ��w���Ă���悤�ɂȂ����B�����S�̔�����M�����悤�ɂނ��A��b�ɍs���l�܂�A�m�I�ɖ��͂Ȃ������B�ɕ肪���鍂�@�\�Δ��B�l�ށH�����w���̐ӔC���Ƃ�N��ɂȂ����V�l�ނƂ��ẮA���̐V���ɏo�����Ă������@�Δ��B�l�ނƂǂ̂悤�Ɍ��������̂��낤���B�܂��t�������B�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���{��ƗÖ@�m����j���[�X 302�A2007/3 |
|
�@���n�r���e�[�V�����̗��O
�@�u���l(�܂�т�)����������V�l(�����т�)��ꐶ���ʂ����̂����Ȃ���Ɓv��N�̉Ăɋ}�����ꂽ�ߌ��a�q��(�Љ�w��)�̈�̂ł���B�����6�N���܂�O�ɔ]���Ǐ�Q�ɂ��Ж�ჂŃ��n�r���e�[�V�����𑱂����Ă��鑽�c�x�Y���i�Ɖu�w������w���_�����Ɓj���A�u����v�z�i2006�N11�����j�v�A�u�@�i2006�N10�����j�v�ɏЉ�ꂽ�B������Ƃ����g���s���R�ɂȂ��A���c���͌��t�̎��R�������Ȃ���A�^���Œɗ�Ȍx�����������Ă���B�����g���s���R�Ȑg�ɂȂ�ꂽ�̌����A���t�ɂ���Ȃ�[�݂Əd�݂������Ă���B������̃��n�r���e�[�V�����Ɋ֗^�����Z���s�X�g������ƕ����B
��N�̃��n�r���e�[�V�������������ɂ́A�����̕��������٘_�������A���Ώ����^���ⓖ������͂��ߊe�c�̂̍R�c�������o���ꂽ�B���n�r���e�[�V�����Ɍg�����E�Ƃ��āA���̐E�\�c�̂̈���Ƃ��āA���n�r���e�[�V�����Ƃ͉���������Ă���B���_�Ȃɂ����Ă��A�O�J���┼�N���Ƃɒ����O�����邱�Ƃőމ@���������A�ē��@�Ƃ����葱���ŋA�@����Ƃ����A�\�ʏ�̓��@���Ԃ��Z�k�����悤�ɂ݂������̍��M���Ă���a�@������B
���Â̂��߂̓��@�͂ł��邾���Z���ɂ��������Ƃ͂Ȃ��B�������A�Ɏ��Ԃ��K�v�ȏꍇ������A�@�\���ێ����邽�߂̃��n�r���e�[�V�������K�v�ȏ�Ԃ�����B��ƗÖ@�m�ɂȂ���4�����I���}����N�̏��߂ɁA�C���Ɉ��|����Ȃ���A���c�x�Y�A�ߌ��a�q�����������ȁu��(��������)�v�i�������X�A2003�j��ǂݕԂ��Ă݂��B�u�P�Ȃ�@�\�P���ł͂Ȃ��A�S�g�ɏ�Q������l�̐l�Ƃ��Ă̕����Ɛ����ւ̎Q���v�Ƃ������n�r���e�[�V�����̗��O�A�����Ŗ₦��ƗÖ@�m�Ȃ�N����������ł��낤���O�����������Տ��̏�ł��肽���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���{��ƗÖ@�m����j���[�X 299�A2006/12 |
|
��ƗÖ@�m�ƃL�����A�|�̂�Y�ꂽ�J�i����
�@�ߔN�L�����A�Ƃ������t���悭���ɂ���悤�ɂȂ����B���̏ꍇ�̃L�����A�́A�P�Ɂu�o���v�u�E���v�Ƃ������Ӗ��ł͂Ȃ��A����̐E�Ƃ�I�������̐E�ƂɊւ�����I�Ȓm����Z�p��g�ɕt����Ƃ����Ӗ��Ŏg���Ă���B���ƌ������̇T�펎���ɍ��i�����G���[�g�������L�����A�ƌĂсA�����m���L�����A�ƌĂ�ō��ʉ���}���Ă���̂��A���I�ȐE�ƂɏA���Ă��鏗�����L�����A�E�E�[�}���ƌĂԂ̂��A���̌ꌹ���e�����Ă̂��Ƃł��낤�B����͂��Ă����A�Z�傪���ׂĂS�N�������A��ƗÖ@�m�Ƃ����E�Ƃ������ڎw���Ă���킯�ł͂Ȃ��w�������w���Ă���悤�ɂȂ����B�ނ�̓�����A��ƗÖ@�̒m�Ȃ�Z�p��g�ɂ����҂��A�o�ŊE��}�X�R�~�A�s���W�ȂǁA��Â╟���̈�ȊO�̗̈�ŕ��L������l�ނ��o�Ă���悤�Ȏ���ɂȂ��Ă����̂ł��낤���B�c�O�Ȃ���A���̂Ƃ���́A���������E�Ɗ���E�ƈӎ����Ȃ��A�Ƃ肠������w�ɓ��w���Ă����Ƃ������x���̊w���������悤�Ɍ����邪�A�ǂ��Ȃ̂��낤�B��ƗÖ@�̗̈悾���ł͂Ȃ��A���{�̍�������S�ʂɂ݂���ۑ�ł��낤���A�����̐l���ɂ�����L�����A�E�f�U�C�����A�S���Ƃ����Ă����قǁA�Ȃ��ꂽ�o�����Ȃ��܂ɒǂ��Ă����B�R������ɂȂ��āA���Ă��ꂩ��ǂ����悤�Ƃ���ƔY�ݎn�߂��Ƃ�������������B����ɂ����Ă��A����Ɍg��邽�߂̂����̃L�����A������A�����̔���Ȃ��L�����A�E�A�b�v�̂��߂̃L�����A�E�p�X�ɁA�����̍�ƗÖ@�m���ǂ���Ă���B�����̐g�̂Ƃ̂ӂꂠ���A�����̐g�̂�ʂ����O�E�Ƃ̂ӂꂠ�����Ȃ܂܁A�g�̂̃��A���e�B��̌����邱�ƂȂ���ƗÖ@������邱�Ƃ̊낤����������B��ƗÖ@�m�ɂƂ��Ă̖{���̃L�����A�Ƃ͉����A�����炽�߂Ė₢�����Ă���B�u�̂�Y�ꂽ�J�i�����v�ɂȂ�O�ɁB
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���{��ƗÖ@�m����j���[�X 296�A2006/9 |
|
�w��̓]�@
�@���N����ƗÖ@�w��܂Ŏc���Ƃ���1�������܂�ɂȂ����B���N�̊w���40���N�Ƃ����킪���̍�ƗÖ@�m����ɂƂ��đ傫�Ȑߖڂł��邾���łȂ��A��ƗÖ@�m��30�A000�l�A���艞���800�l���A�w��Q���\�萔5�A000�l�A����̍�ƗÖ@�m50�A000�l�A100�A000�l����Ƃ������\�L�̔����J����d�v�ȉۑ��������w��ł���B����������Ƃ��āA�w��]�c�ψ���𒆐S�ɐ��N�O�̊w��猟�������݂��Ă�������⍸�ǂւ�IT�V�X�e���̗̍p�A�����ď��̎��݂̏��^�W��CD-ROM���ȂǁA����܂łƂ͑傫���قȂ�V�X�e�����������̗p���ꂽ�B���萔��500���x����700�������_�ŁA�^�c��Ƃ͑��c��x���ōs���Ă������Ƃ��A���A�Ƃ͂���Ȃ��܂ł��}�ɍ���x���ōs��Ȃ�������Ȃ��悤�ȑ傫�Ȓi����̌������B���W�c�Ö@��12�`13�����x�܂łȂ�Ȃ�Ƃ��@�\���Ă����O���[�v�_�C�i�~�b�N�X���A15�������Ƃ���ɓK�ɋ@�\���Ȃ��Ȃ邠�̑̌��ɂ����Ă���B�C���[�W�����̌��Ƃ����Ă��悢���낤�B���̋��s�w��̎��s�ɂ��A�V���Ȏ���ɂނ����V�X�e���̗��_�Ɖۑ肪��̓I�Ȃ��̂ɂȂ�Ɗ��҂����B����2�A500���A����600�����܂�̍��ǎ҂̑I��A���ǂ̎��ƌ����A�C�O����̎Q���҂�����A���E��Ȃǂ̎��O�o�^����щ��艞��A���q�ƃ|�X�^�[�Ȃǂ̔��\���@�A���s�����ʼn\�Ȕ͈͂ȂǁA�����ۑ�͂��肪�Ȃ��B�C���^�[�l�b�g���p�A�������A�o�ϐ��A����������̗���ł��邪�A���̂��߂ɁA�ЂƂƂЂƂ̂ӂꂠ���A�\���Ȉӌ��̌����Ƃ������A��ƗÖ@�̕����̏n���ɂƂ��đ�ȋ@��ɂȂ�댯�������Ȃ��炸�͂��ł���B�����̉�����A�V�����V�X�e�����ǂ̂悤�ɐ��������A����̐V���Ȏ��s���y���݂Ȃ���A�w��̓]�@�����悢�`�Ŕ��W�I�ɏ��z���邽�߂̒�Ă�����Ɋ��邱�Ƃ����҂���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���{��ƗÖ@�m����j���[�X 292�A2006/5 |
|
��́u�����@�������v�̌�
�@�R���ɐ��N�ꏏ�Ɋw��ł���ƍ�ƗÖ@���傭�炢�ɂȂ����w���𑗂�o���ƁA�S���ɂ͂܂�������w�������w���Ă���B�w���ł̊w�т͑唼���ǂޒ������Ƃ𒆐S�ɁA�����o���ނ����킹�Ęb���������ƂɂȂ�B�����Տ��̌��Ō��w�Ȃǂ����邪�A�w���ɂƂ��Ă͓��̒��̊w�K���S�ɂȂ�A������Ȃ��B�������Ċw�N�i�s�ɂ�A�Տ����K�̎��Ԃ�������ƁA��̓I�ȑ̌������Ď�������B���K��ŁA�����������߂Ēm�����悤�Ȃ��Ƃ����ɂ��A�ꐶ��������������̋��������]������w�������邪�A����������w�K�������҂́A�u�����@�������v�Ɠ��ł킩���Ă������̂��������A�X�g���Ɛg�̓��Ɏ��܂�o��������B�Տ��ɏo�āA���낢��o�����[�܂�ƁA���x�͊�O�̌��ۂɂƂ���Đg�������ł��Ȃ��悤�ȁA�ǂɍs���������Ԃ�����B���������Ƃ��ɁA�w�p�W��⌤�C��ȂǂŘb������A���̐l�ƈӌ�����������ƁA��������������Ǝ��g��ōs���l�܂��Ă���҂قǁu�����@�������v�ƁA��u�ɂ��Ėڂ̑O����������ƊJ����悤�Ȍo��������B�v�l����̌��A�̌�����v�l�A���̉ߒ��Ő������́u�����@�������v�̌��́A�h�C�c��ł����̂܂�"Ach so !"�Ƃ����B�p��ł�"Oh, I see !"�ɂ�����̂��낤���B�v�l�w�K�Ƒ̌��w�K�A�����ꂪ��ł����Ă��A�S�g���ւ̌J��Ԃ��ɂ��A�v�l���s�ׂɂȂ�A�s�ׂ��v�l�Ƃ��Ă܂Ƃ܂邱�ƂŁA�u�m���Ă���A��������A�ł���A�g�������Ēm��v�A�v�l�ƍs�ׂ���̂ƂȂ��ďK���������v���Z�X����ށB���̏K�����́A����̐g�������čs�����ƂȂ��ɂ͐��藧���Ȃ��B�v��ʕa���Q�ŁA�S�g�̋@�\�ɘc�݂��������l�������u�����@�������@������������̂��v�Ǝ������Đ������Č�����鉇���������ƗÖ@�̖L���ȓ��퐫��������B���N���w��߂Â����B�w��ŁA�Տ��̍s���Â܂���u�����@�������v�̌��ɕς��悤�B�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���{��ƗÖ@�m����j���[�X 290�A2006/3 |
|
�@end�i�I���j��end(�ړI)�|�s�f�̔N�Ɍ����ā|
�@�ی���Õ��������ł͂Ȃ����A�傫�ȓ]�����n�܂��Ă��钆�ŁA�ߑオ�z���Ă������̂̏I��������v��������N�ł������B�ߑ�̍s���l�܂�́A20���I�Ō�̎l�����I�ɘI��ɂȂ������̂ł��邪�A����Ƃ��̂�����݂̍Ō�̂������ɓ��B�����̂��낤���B
�@���ی��A�V��Q�Ғ����v��A�ی���Õ����̉��v�r�W�����A�O�����h�f�U�C���A��Q�Ҏ����x���@�ƁA�킪���̕ی���Õ����̍s���l�܂��ŊJ���邽�߂Ɏ��X�Ǝ{�ł��o����A���ی��͑������s���l�܂�A���{�I�Ȍ��������n�܂��Ă���B
�@�I���Ȃ̂��A�͂��܂�Ȃ̂����f�����Ȃ��悤�ȍ��ׂƂ�����Ԃɂ�������B�������Aend���u�I���A�Ō�A�����A�I���v�Ȃǂ�{�`�Ƃ��Ȃ���A�J���g�N�w�Łu(���ɂ�)�ړI�v���Ӗ�����悤�ɁA�������́A���̏I���̂������̂悤�ȓ]������end�̒��ɂ����Ă����A���ɂ�end�i�ړI�j�����������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�u���@��ÁA�{�ݏ�������n�搶�����S�ցv�u�����Љ�v�u�����T�[�r�X�̈ꌳ���v�u�P�A���l�W�����g�v�u���ʂ̊T�O�Ƃ��Ă�ICF�v�A�Ȃǂ̃L�[���[�h�́A���n�r���e�[�V�����̏d�v�Ȉꗃ��S���Ă�����ƗÖ@�ɂƂ��ē��ʐV�������̂ł͂Ȃ��B�V�����͂Ȃ����A�f���邾���̌P���̂悤�Ȃ��̂ł������B���ꂪ�A���A��̓I�ȋ��ʂ�end�i�ړI�j�Ƃ��Ď��グ��ꂽ�Ƃ����Ă��悢�B��w�̒m���ƋZ�p�������ĐS�g�̋@�\�̏�Q�Ɛ����̏�Q�ɂ�������ƗÖ@�m�ɂƂ��āA���������ē����������̊�H�͍ő�̃`�����X�ł�����B����̊�{���j�Ƃ��đł��o���ꂽ���̃`�����X���������Aendo to end�Ŏ��g�݂����B���{��ƗÖ@�w�40����}����V���ȔN���A�s�f�A�������ƂȂ��A��ƗÖ@�̎��Ɨʂ̂͂��܂�̔N�Ƃ������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���{��ƗÖ@�m����j���[�X 286�A2005/12 |
|
�@�u�@���v�Ɓu�Â��v
�@�u�����M�Ȃ炸�v�u�����͈Ղ��s���͓�v�Ɓu�s�����s�v�Ƃ��������́A�������̍������{���L�̂��̂ł��邪�A�����ČŗL�̂��̂ł͂Ȃ��B���̃V�F�C�N�X�s�A�́u�w�����[�����v�̂Ȃ��ɂ��A"And
'tis a kind of good deed to say well; And yet words are not deeds�B�iHenry
�[, �V�B �A�B 153-4�j"�Ƃ����䎌������B���Ȍ����͂悢�s���̈�ł��邪�A��͂�s�ׂł͂Ȃ��Ƃ������Ƃł��낤�B�܂��A"Deeds,
not words�B "�Ƃ����������B���ׂ����ɂ͂��ꂱ�ꌾ����蒼���Ɏ��s����A�������́A���t���s�ׂł��̐l�����킩��A�Ƃ������Ӗ������ł���B
�@���E�̈Ӓn�̒��荇���ŋ�Ԃ����܂�A�������}�����������x���@���摗��ɂȂ����̂͂������A���_�ی������@��f�Õ�V�̉����ȂǁA�������̑�ȐR�c���摗�肳��邱�ƂɂȂ����B�s�����������Ƃ́u�ق��Č�炸�v�A���Ƃ���Β��q�̂悢���Ƃ����������́u�L���s���s�v���A���R�t���̂��߂Ɂu�����������������v�k�ق�M����A�Ƃ��������Ƃ������Ƃ݂ɑ����Ȃ����悤�Ɏv�����A�C�̂������낤���B
�@����������Ȃ��Ă��A��̕��͋C��ǂݎ��A����ꂽ���t�̂Ȃ��ɐ^�ӂ����ݎ��Ƃ������u�@���v�̕���������A����Ȃ��Ă��������ė~�����Ƃ������n�ȁu�@���v�̉������A������u�Â��v�̕����̖��n�Ŏ��Ȓ��S�I�Ȉ�ʂ��\�ʉ����Ă���B����̈ڂ�ς�������A�u�@���v��u�s�����s�v���A�����̐��A���Ȏ咣�����߂���悤�ɂȂ�������A�u�L�����s�v�A���߂āu�ꌾ���s�v�����ꂼ�ꂪ�s�Ȃ��������̂ł���B�u�q�͐e�̔w�������Ĉ�v�Ƃ����B����E�����҂����ł͂Ȃ����A�����ގ҂́A�p���邱�ƂȂ��w�����������鐶�����������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���{��ƗÖ@�m����j���[�X 284�A2005/9 |
|
���ߑ�����̏��i��
�@�́X�A���̂قƂ�ǂ��l�ɂ����`���ɂ����̂������B�q�ǂ��̍��A�c���̉Ƃɂ͉z���x�R�̒u����i300�N�ȏ�O�Ɏn�܂����ƒ�z�u��j������A�N�Ɉ�x��̓���ւ��ƏW���ɗ��Ă����B�����D�ƈꏏ�ɂ��낢��Ȋe�n�̘b�����B���W�I��V���Ȃǂ̖�����������́A����������◷�l�A��r�Ȃǂ�����`���Ă����̂��낤�B���������J���̓������{�ł́A�����̊w���|��A�����邾���ŁA�I���W�i���e�B�������Ă��w�ґR�Ƃ��Đ��v�𗧂ĂĂ���҂������B�O���Ƃ̏��i���𗘗p���������p�ł���B
�@����i���݂ł́A�̂Ƃ͈Ⴄ�`�ŏ��i�������܂�Ă���B����̏��i���́A���̔×��ɂ��K�ȏ���I���ł��Ȃ��A��@�Ȃǂ̖��ŏ������ł��Ȃ��A������肷��w�͂����Ȃ��A��������̓`�B�Ȃǂɂ��K�ȏ���L����Ȃ����Ƃɂ��B���i�������Ɋւ���@���A�l���ی�@�ƁA���̓K�Ȋ��p�ƊǗ�������鎞��ɂȂ����B����⌧�m��A�w��A���C��Ȃǂ̊����ɂ��Ă��A���i���͌���݁A�v��ʖ��������N�����B������������ł��邪�A���p�����X�����e��ǂݎ��͂�{���A�ϋɓI�ɃR�~���j�P�[�V������}��w�͂��K�v�ł���B
�@�Տ������Ȃ��狳��E�����Ɍg���҂̂P�l�Ƃ��ẮA���ɐU���邱�ƂȂ��A���i���ɂ�������������Ƃ��Ȃ��悤�ɂƐS���Ă���B�l�̐����Ɋւ����E�Ƃ��āA��ɐV�����m����Z�p��ǎ��E�����Ȃ���A�I���W�i���e�B�̂���d����S���������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���{��ƗÖ@�m����j���[�X 281�A2005/6 |
|
�h�s���[�̋����Ǝ����F��[�̏d�݂���������
�@2002�N�ɓd���I�L�^�����[�@���������čs���u�n���I���d�q���[����@�v�i���́j���{�s���ꂽ�B���N�A�V���s���E�s�c�I���œ��{���̓d�q���[�����{���ꂽ�B�d�q���[�̂˂炢�́A�������ɂ��^��[�△���[�̉��P�A�J�[�����̍������Ɠ��[�����グ�邱�Ƃɂ���B�n���I���d�q���[�́A�I���l�̎��R�ӎu�ɂ�铊�[����邽�߁A�I���l�����[���ɂ����ēd�q���[�@���������ē��[������@���Ƃ�ꂽ�B
�@�C���^�[�l�b�g���[�́A���[���ł̓��[���`���t�����ɁA�l�̏��L����R���s���[�^�[���i�g�ѓd�b������\�ɂȂ�j���瓊�[�ł���Ƃ������̂ł���B���̕��@�����߂Ď��݂�ꂽ�̂́A2000�N3���ɍs��ꂽ�č��A���]�i�B�̖���}�哝�̗\���I���ŁA�\�z���铊�[���ł������B1990�N�㔼����}���ɕ��y���n�߂��C���^�[�l�b�g�́A���̗��ւ��ƂƂ������ɉB�ꂽ�A������B2003�N�̃I�[���X�^�[�C���^�l�b�g�t�@�����[�̐�茛���Y��ʓ��[�����A2004�N���̃l�b�g�I�[�N�V�������\�����Ȃǐ�����Ȃ��B�C���^�[�l�b�g���[�ɂ����Ă��A�f�[�^�̉�₂��d���[�E�Ȃ肷�܂����[�̖h�~�A���[�̔閧�A�Z�L�����e�B�A�{�l�m�F�Ȃǂ������̉ۑ肪����B���̂��߁A�h�c�E�p�X���[�h�̌l�����s�Ȃǂ��낢��ȍH�v���Ȃ����B
�@������ɂ���A����Q���҂����̓��[�ɂ�����Ă����]���̕��@���炷��A������������̈ӎv��\���ł���B�������A�����̐��̑�َ҂ƑΛ����邱�ƂȂ����[���邱�Ƃɂ��Ȃ�B���鋕���ɘf�킳�ꂸ�A���̈�[�̏d�݂������������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���{��ƗÖ@�m����j���[�X 278�A2005/3 |
|
NBM��EBM
�@�@������̕a���ɑ��鎡�Âł��������Ă����i���e�B�u�E�x�C�X�h�E���f�B�X���iNarrative Based Medicine�ANBM�j���A�������N�̈���Ă���������悤�ɂȂ��Ă����BNBM�́A���̐l�����̌��́u�����v����A�u��܂��v��u���傤�����v�̕����𗝉����A���̐l�̕�������ɃA�v���[�`����Z�@�ł���B���₱������嗬�s��EBM�iEvidence
Based Medicine�j�́A�u�q�ϓI�f�[�^�Ɋ�Â��Đf�f�⎡�Â��s�����Ɓv�ŁANBM�Ƃ͑ɂɂ���悤�Ɍ����������������B�������u�ŋߍŐV���ŗǂ̍�����ǐS�I�ɐ��������Ăɂ������āA�X�̊��҂̃P�A�ɂ��Č��肷�邱�Ɓv�iSackett�A1996�j��EBM�ł���ANBM�͂������������ⓝ�v�A�Ȋw����₢�A���҂̌o���ƈ�w�I�f�[�^�̋��n����������̂ŁAEBM�ɂ͕s���Ȃ��̂ł���B
�@��̑O�̊��҂̌�镨��ɂ������莨���X���i�X���j�A���d���A���߂���Z�p�́A�Տ��Z�\�̒��j�ŁA�ΏێҒ��S�̈�Â̌��_�Ƃ����悤�B�����ŏd�v�Ȃ̂́u������v���ƂƁA��������̐l�̋C�������v�����Ȃ���u�����v�҂����邱�Ƃɂ���B�\�����Ȃ��u��܂��v��u���傤�����v�A�o���ʗ��Ȃǂ��܂��܂ȃG�s�\�[�h���d�Ȃ��āA�����́u����v���a�������B���́u������v���ƁA�����Đ�����킸���́u����v�̋C���������������Ă��炦��A���ꂪ�����ɋN�������Ƃ̊m�F�A���ɂȂ�A�����Ă����Ƃ��āA�����ւ̕�������^����͂Ƃ��Ȃ�B
�@����A�u������v���Ƃ́u���v����u�x��v�A���Ȃ킿�����̓s���̂����悤�ɕ�������グ��A������storytellig�ɂȂ闎�Ƃ���������B�F�m�ǂɂ݂���u�������ϑz�v�ⓝ�������ǂ́u�W�ϑz�v�Ȃǂ́A�u��܂��v�̒��ɂ����鍢�f�ɑ���Ώ��s���ł���storytellig�ł͂Ȃ��Bstorytellig�͎��ȐӔC���Ƃ邱�Ƃ��ł���҂��A������₲�܂����A�i���V�Y���A���Ȍ����Ȃǂ���s���s�ׂł���B���ÁE�����Ɍg���u�����v���ɂ���҂ɂ́A���i���j�������邠�܂��������Ɠs���悭��������storytellig�̗U�f�Ƃ���㩂�����B��ɒN�̂��߂ɁA���̂��߂ɂ�Y�ꂸ�AEBM�̍����Ƃ��Ă�NBM�������������B
�@2004�N�A�킪���͑����̍ЊQ�Ɍ�����ꂽ�B4���ɃJ�����������Ŕ���������1���䕗�X�[�_�G�Ɏn�܂�A11�����܂ł�25�̑䕗���������A���̂���10�����{���P�����B�Z��⓹�H�A�앨�Ȃǂɑ傫�Ȕ�Q���c���A����ɍ�N�̋{�鉫�n�k�ɑ����ĐV�������z�n�k���������A�V�����̎R������n��ɐr��Ȕ�Q��^�����B�����̊F�����܂��܂ȉۑ��S�g�̒ɂ݂�����ĔN���z�����B���ꂩ�炱�̑̌����u������v�����K���܂łɁA�S�g�̔�J���A���X�̕�炵�̒��Ɍ���n�߂�B���N�ɗ��ӂ���ĐV�����t�����}�����������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���{��ƗÖ@�m����j���[�X 275�A2004/12 |
|
QQOT�F�ʂ�����
�@6�����j���[�X�̘_�d�ɍڂ����uQQOT�F�ʂ����ցv�Ƃ��������ɑ��A��B����u�V�k�S�Ȃ��炠�Ȃ��̍l���鎿�Ƃ́v�Ƃ������b�������������B�}���ɔ�剻�����ƗÖ@�E�̌���������Ă̂��S�z�ł���B����⌤���A�E�\�c�̂Ƃ��Ă̋Ɩ��Ɍg���悤�ɂȂ�A�����Տ��Ɋւ��Ƃ��������ł͂Ȃ��Ȃ������A���͍�ƗÖ@�m�ł���B��������A�������A����Ɩ����N�����S��Ȃ���Ȃ�Ȃ��d�v�Ȃ��ƁB�T1����2���ł����Ă��Տ��̎�͔����Ȃ��B�����͂�������A��ƗÖ@�̎��ÁE������K�v�Ƃ���Ă�����X�ɁA���悢�T�[�r�X�����A���̗Տ����x���A���̗Տ��̋Z�p�����߂邽�߂ɂ���ƍl������ł����B�u�ǎ��ȋx���̏�̒v�Ɓu���X�̉c�݂ɕK�v�Ȋ����̍đ̌��v��ʂ��āA���̐l���炪������Ӗ��A�����Ă����Ӗ��ɂӂ����ыC�����������A�v��ʕa�����Q�ɂ�莸���A������߂������������������߂��A�����̏�ɖ߂��Ă��������B�u���Ȃ��i��ƗÖ@�m�j�ɉ�Ă悩�����v�u�����i��ƗÖ@���j�ɗ��āA������x�撣���Ă݂悤�Ƃ����C�����ɂȂ�܂����v�����S����v���Ă���������A����ȑΏێ҂ւ̂܂Ȃ����Ɗm���Ȓm���E�Z�p�A���ꂪ�����v����ƗÖ@�́u���v�ł���B�������������b�ɑ��ẮA���̂悤�ȏ璷�Ȃ������͕K�v�Ȃ������B��������Ĉꌾ�ł��Ȃ�����u�����ˁA�������͂��̊�{���������Ă͂����Ȃ��v�B�ӂƂ����C�̂��݂�OT�}�C���h��OT�Z���X��u���Y��邱�Ƃ��Ȃ��悤�ɂ������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���{��ƗÖ@�m����j���[�X 272�A2004/9 |
|
�ǂ̂悤�Ȏ��ւƖ����
�@�u��W���Ă���W���Ă���ƗÖ@�m�����Ȃ��B���̗����ˁv�ƁA������ߌ����Ŗ��N�̂悤�Ɍ���ꂽ���オ�����������B�ߔN�A��Î{�݂���̂����������͏��Ȃ��Ȃ������A�����W�ł͂܂����ܕ������Ƃ�����B��ƗÖ@�m�����̍��ɒa�����āA1000�l�����̂�16�N�ځA2000�l�����̂�20�N�ڂ̔N�������B�{���Z�������A���Ǝ҂������n�߂������ɂ͈��g�����B10,000�l�����̂��A6�N�O��33�N�ځB���N�́A�L���i�҂�26,000�l���A���w�����6,000�l�̑��ɂ̂����B���͗́A�ʂ̑����͊m���ɍ�ƗÖ@�m�Ƃ������̂ɑ���Љ�I�F�m�x�����߂��B�������A�a������40�N�ɂȂ낤�Ƃ�����E�̔����ȏオ�o��5�N�����Ƃ�������ȐE�\�W�c�ł�����B�{���Z������w����̐��_�c����A�ǂ̂悤�Ɏ������邩���ۑ�ł��邪�A�����Ƃ��傫�ȉۑ�́A���̂��F�m����͂��߂��Ȃ��ŁA���̋}������ʂ��ǂ̂悤�Ɏ��Ƃ��č��߂邩�ɂ���B�u����ƍ�ƗÖ@�m�������ɂ����Ă����悤�ɂȂ������ǁA�K��ɍs���Ă��t�قȎ�H�|�ł͖��ɗ����Ȃ�����ˁv�ƒn��P�A�ɔM�S�Ɏ��g�ގ{�݂̒����猾��ꂽ�B����ȃp���`�ł���B�N��6,000�l���܂�̑�ʐ��Y���A�u�����낤�A�����낤�v�̑�ʏ���ɏI����Ă͂Ȃ�Ȃ��BQQOL�Ȃ��QQOT�iQuantity
and Quality of Occupational Therapists�F����j���l���鎞����}���Ă���B�ǂ̂悤�ȁi���j��ƗÖ@�m���A�ǂꂾ���i�ʁj���ɋ����ł��邩������Ă���B���U���琧�x�̎��݂��n�܂��Ă��邪�A�`��������w�ԕ����A���炭�͎��s���낪�����B��]����ł��邪�A��]�ɂ͒�ĂƎ��H�����Ăق����A�e���m��̋���S���҂̓l�R�̎�ǂ��납���̎���肽���v���Ȃ̂ł͂Ȃ����낤���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���{��ƗÖ@�m����j���[�X 269�A2004/6 |
|
�j���[�g���̃����S�̖i�ߑ�Ȋw�j�Ǝ��
�@�N�n�߁A�j���[�g���i1943�`1721�j�̃����S�̖��}����ڂ��ō����ɑ��������Ă���Ƃ����L����V���œǂB�e�́A40�N�قǑO�ɉp���̍���������������蓌����w�t���A�����ɑ���ꂽ���̂Ƃ����B�j���[�g�������L���̖͂@�������邫�������ƂȂ��������S�i�i�햼�F�P���g�̉ԁj��5��ڂƂ����Ă���B���̎����̔@���͕ʂɂ��āA�����S�ɂ����ɂ��n���Ɍ������ė�����͂������Ă��邪�A�^���̊����̓����ŁA���͗������ɒn���̎��������Ă���Ƃ������L���̖͂@�����������ꂽ�B���̔����ɂ��A�ߑ�Ȋw���n�܂�A�Ȍ�A���R�Ȋw�͕��Ր������߂邱�ƂŔ��W���Ă����B
�@�������l�X�Ȍ��ۂ̓�������������Ă����ߑ�Ȋw���A���\�ł͂Ȃ��B�q�ϓI�ɓ������́����ՓI�ƌ����Ă��邱�Ƃ��A�����ɂ͂��̑����͗ގ��̔��e�̂��Ƃł���A���̗ގ��̔��e���ǂ��܂œ����Ƃ��邩������A���Ր��������܂��Ȃ��̂ł���B��ƗÖ@�́A�����̑��l�Ȍ��ۂ�ΏۂɁA�����̎��̈Ⴂ�̖�����舵���B�u����͑��v�����A���̊����͏�������v�ƁA��ςƂ��Ă͖��炩�ɂ���Qualia�̈Ⴂ�𑨂��Ă��Ȃ���A�q�ϓI�ɂ��̈Ⴂ�����t�ŕ\�����邱�Ƃ�������Ƃ�evidence������B����͎��R�Ȋw�Ƃ͈قȂ�Ȋw�ł���B���̑Ώۂ⌻�ۂ�afford���Ă���Qualia�𑨂��邱�Ƃ̓������y������Ƃ������A��������ƗÖ@���̂Ă��Ȃ����R��������Ȃ��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���{��ƗÖ@�m����j���[�X 266�A2004/3 |
|
�č��ɂ����鐸�_�ی��̈��ƗÖ@�̜f�r�|�̂�Y�ꂽ�J�i�����H�|
�@�č���ƗÖ@����iAOTA�j2003�N�x����̏��F�����̈�ɁA���_�ی��̈�̍�ƗÖ@�Ɋւ�����̂��������B����́A�@��K���ɂ���Qualified Mental Health Provider�^Professionals�������͂���ɑ�������p��ɁA��ƗÖ@�m���܂܂�Ă��邩�ǂ�����������悤��AOTA����ɗv���������̂ł���B20���I�O���ɐ��_�q���^���̈�Ƃ��Ďn�܂�����ƗÖ@�ɑ��A���_�ی��Ɋ֘A����Ö@�̈�ł���Ƃ����F�����Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���B����B�A���_�ی��ɊW����l�����ɁA��ƗÖ@���L�p�ł��邱�ƁA��ƗÖ@�̊��p���[�ւ��悤�Ƃ�����|�ł���B
�@����č��Ő��_�ی��̈�ō�ƗÖ@�ɏ]�������ƗÖ@�m��5���O��A����u��ƗÖ@�m�͐��_�ی��Ɋւ����E�̈���ł��邱�Ƃ�F�����Ă��������v�Ɛ����グ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��قǁA�č��ɂ����鐸�_�ی��̈�̍�ƗÖ@�͒���E�f�r���Ă���B�����͂��낢��l�����邪�A��ɂ́A�G��A���|�A���y�A���N���G�[�V�����ȂǁA�������Ƃɐ��E��{�����A��ƗÖ@�m���A��Ɗ�����p���Ȃ��Ȃ������Ƃ��e�����Ă���B�����āA�킪���̂悤�Ȍ��I�ی����x���Ȃ��A���ԕی��ɂ��}�l�[�W�h�E�P�A�ɂ����āA��Ó��e�E��Ê��Ԍ���ɋ������������ی���Ђ��A���Ԃ�v����Ö@�Ⓖ�ړI���ʂ��m�F���ɂ������̂�f�ÑΏۂ���͂����Ă������Ƃ��e�����Ă���B
�@�������\������L���Ŋm���ȍ�Ɗ����Ƃ�����i�����A�����̍Č��A�����ƓK������������͂��̍�ƗÖ@�m���AADL�ȊO�̍�Ɗ�����p���Đ����̏�Q�Ɋւ�邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ����B��Ɗ����������Տ����ł��Ȃ��A���Ȃ��A�������̍�ƗÖ@�m�́A�u�̂�Y�ꂽ�J�i�����v�������݊����Ȃ��B�����a�������{�̍�ƗÖ@����E�Տ���I�ޑO�ɁA��ƗÖ@�m�Ƃ��Ă̎��o�ƑK�v�ł���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���{��ƗÖ@�m����j���[�X 263�A2003/11 |
|
��ƗÖ@�̃��j�o�[�T���f�U�C����
�@1982�N�A�u���A��Q�҂̏\�N�v�Ɋ�Â��A��Q�Ҏ{��Ɋւ��鏉�߂Ă̒����v��u��Q�ґ�Ɋւ��钷���v��v�����肳��A���̌�p�v��Ƃ���1992�N�ɍ��肳�ꂽ�u��Q�ґ�Ɋւ���V�����v��v�́A���N�������ꂽ�u��Q�Ҋ�{�@�v�Ɋ�Â���Q�Ҋ�{�v��Ɉʒu�t����ꂽ�B�����̌v��ɂ��1995�N�̏�Q�҃v�����ł́A�킪���̏�Q�Ҏ{��̕���ŏ��߂Đ��l�ڕW���f���m�[�}���C�[�[�V�����ƃ��n�r���e�[�V�����̗��O�����i����Ă����B�����āA��N�����̗��O�������p���A��Q�҂̎Љ�ւ̎Q���A�Q��Ɍ���2003�N�x����2012�N�x�܂ł�10�N�Ԃ̊�{�I������������Q�Ҋ�{�v��ƁA�V��Q�҃v��������߂�ꂽ�B���̏d�v�ȃL�[���[�h�́u�����Љ�v�ł���A���NWHO�ō̑����ꂽICF�i���ې����@�\���ށj�̊��p��}��A�����A�ړ��A���A���x�A���s�A�S���Ȃǃ\�t�g�A�n�[�h���ʂɂ킽��Љ�̃o���A�t���[����i�߂�Ƃ��Ă���B
�@�����ɂ́A20���I�ɐ�啪�������ꉻ���邱�ƂŔ��W�𐋂������ꂼ��̕��삪�A��x��������A�̈�Ƃ������E������A���ׂĂ̂ЂƂɕ�����₷�����j�o�[�T���f�U�C���ւƂ����A�V��������̗����������B�ЂƂ̓��X�̕�炵���\�����邳�܂��܂ȍ�Ƃ����ÁE�����̎�i�Ƃ����ƗÖ@�́A�����A�J���A�]�ɁA��i�A���Y�A��V�d�d�Ƃ��������}�œ���I�Ȗ�肪�A���ÁE�����Ƃ��������I�ȍ\���̒��ɓ��肱��ł���B���̕��}���Ɠ��퐫�䂦�ɁA��啪�����邱�Ƃł߂��܂������W�𐋂��Ă����ߑ��w����Ȋw�������A�O���I�̌㔼�A���E�̍�ƗÖ@�E�͗��_��f���̍\�z�ɑ傫�ȃG�l���M�[�������Ă����B��������ƗÖ@�́A�Ɩ��Ɛ�ł͂Ȃ��A���̓Ɛ�Ƃ��Ĉʒu�Â����Ă���悤�ɁA�{�����j�o�[�T���f�U�C���Ȃ̂ł���B��ƗÖ@�̗��_��f�������j�o�[�T���f�U�C�������A���̒��ŋ@�\����v���t�F�b�V���i��������Ă�����ƗÖ@�̖����͂���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���{��ƗÖ@�m����j���[�X 260�A2003/9 |
|
ZIZI-YAMA  |
| |